📰 はじめに
政府が初めて実施した「職業別の年収調査」によると、
医療・介護・運輸・接客など、
社会を支えるエッセンシャルワーカーの平均年収が他職種より
約100万円低いことが明らかになった。
しかも、年齢別に見ると50〜59歳で格差が最も大きく、
200万円以上の開きがあるという。
「社会に必要な仕事なのに、なぜ報われないのか?」
この記事では、その背景と今後の課題を掘り下げていく。
💰 そもそもなぜ他の業種より年収の格差があるのか?
① 価格転嫁ができない構造
医療・介護・運輸・接客といった業種は、値上げ=利用者負担増に直結するため、
人件費を上げづらい構造になっている。
「安くて当たり前」という社会意識も、給与上昇を抑えてしまう一因だ。
② 非正規雇用が多い
これらの業種ではパート・契約社員・派遣社員が多く、
賞与・昇給・退職金などの制度が乏しい。
全体の平均を押し下げる結果となっている。
③ 「尊いが儲からない」構造
人の命や生活を支える仕事ほど、利益を生みにくい。
やりがいはあっても、給与に直結しにくいという“構造的な矛盾”がある。
④ 労働組合や交渉力の弱さ
小規模な事業者や個人雇用が多く、
賃上げ交渉が機能しにくい環境にある。
📊 50~59歳はより顕著に。なぜ?
① 昇給カーブの頭打ち
エッセンシャルワーカーの多くは、40代半ばで昇給が止まりやすい。
現場中心の評価制度では、年齢を重ねても給与が伸びにくい。
② 管理職ポストが少ない
「現場の延長線上に管理職がある」構造で、
責任だけ増えても年収が大きく上がらない。
一方、ホワイトカラー職は役職手当で一気に年収アップ。
ここが50代での差を拡大させている。
③ 再雇用・嘱託での収入減
定年延長により60歳前後も働く人が増えたが、
再雇用では給与が定年前の6〜7割に下がるケースが多い。
特にエッセンシャル職にその傾向が強く、
平均年収を押し下げる。
④ 資格の“天井効果”
介護福祉士・保育士・看護師などは資格を取った瞬間がピークになりやすく、
それ以上のキャリアアップが少ない。
ITや金融のように年齢とともにスキルが評価される業種とは対照的だ。
⚠️ 格差があることについて今後問題になること
🏛 今後どうすれば格差はなくなるのか?
① 公的価格の引き上げ
介護報酬・診療報酬・保育士給与など、
国が決める「公定価格」を見直す。
財源の確保と段階的な賃上げが不可欠。
② 賃上げインセンティブの拡充
賃上げを実施する企業に対して税控除・補助金を強化。
短期ではなく、継続的な支援を行うことで実質的な底上げを図る。
③ キャリアアップの明確化
上級資格やマネジメント職など、
年齢とともに給与が上がる仕組みを作る。
「成長が報われる」職場でなければ人材は定着しない。
④ 社会意識の転換
「安さ」よりも「適正な対価」を。
エッセンシャルワーカーの待遇改善は、
最終的には私たちの安心を守る投資でもある。
✍️ まとめ
エッセンシャルワーカーの給与格差は、
単なる業種の違いではなく、社会構造のゆがみそのもの。
50代で格差が最も広がるのは、
“昇給の頭打ち”と“管理職制度の壁”が同時に表面化するからだ。
だが、彼らがいなければ社会は回らない。
報酬で支える社会へ──。
それが今、私たちが本気で向き合うべきテーマだ。

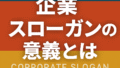
コメント